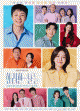JAXA、野口聡一宇宙飛行士ISS長期滞在中の活動をダイジェストビデオで公開
宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙ステーション・きぼう広報・情報センターは、ビデオライブラリ「SPACE@NAVI-Kibo WEEKLY NEWS 第105号」を公開、野口聡一宇宙飛行士のISS長期滞在中の活動をダイジェストで送る。
同宇宙飛行士は、2009年12月21日午前6時52分(日本時間)、ソユーズ宇宙船(21S)に搭乗し、カザフスタン共和国のバイコヌール宇宙基地から、オレッグ・コトフ、ティモシー・クリーマー両宇宙飛行士とともに、国際宇宙ステーション(ISS)に向けて打ち上げられた。
12月28日、「きぼう」日本実験棟で、文化/人文社会科学利用パイロットミッションである「宇宙庭」を、最初の水やりを行うことで栽培を開始。
同実験は、きぼうにおける宇宙庭の作庭による自然観の創出と地上の庭との比較を行うことにより、人類と自然の関係、地球のかけがえのなさを浮き彫りにすることを目的として行われた。
2010年1月6日、きぼう日本実験棟船内実験室内で、組立てが完了したきぼうロボットアームの子アームをエアロック内に収納。
1月13日、きぼう日本実験棟船内実験室で、マランゴニ対流実験(マランゴニ対流における時空間構造)の供試体の補修作業を開始。同実験は、マランゴニ対流(表面張力により引き起こされる対流)のメカニズム解明に向けた基礎データの取得が目的で、補修作業の完了後に実験が開始された。
2月には、スペースシャトル「エンデバー号」によるISSの組立フライトである「STS-130ミッション/国際宇宙ステーション(ISS)組立ミッション(20A)を行い、「トランクウィリティー」(第3結合部)とキューポラを運搬してISSに取り付けた。
2月24日、きぼうと日本をつなぐ日本独自の双方向通信システム「衛星間通信システム」(ICS)が本格稼動。ICSを経由した交信が筑波宇宙センター(TKSC)のきぼう運用管制室との間で行われた。
3月2日、「微小重力環境でのナノスケルトン作製(NANOSKELETON1)」実験を開始。微小重力環境を利用して高機能多孔質骨格構造体(ナノスケルトン)を実現し、低コストで高効率な太陽電池材料の創製や有害物質除去など、環境・エネルギー問題の解決に貢献することを目的とする。
3月11日、ティモシー・クリーマー宇宙飛行士とともに、きぼう日本実験棟ロボットアームの子アームを船外に搬出する作業を行った。
3月18日、ジェフリー・ウィリアムズ、マキシム・ソレオブ両宇宙飛行士が搭乗したソユーズ宇宙船(20S)が分離し、オレッグ・コトフ、野口聡一、ティモシー・クリーマー宇宙飛行士は、3人体制でのISS第23次長期滞在を開始した。
4月4日、ISSにソユーズ宇宙船(22S)がドッキングし、第23次長期滞在クルーは6人体制になった。
4月7日、ISSにスペースシャトル「ディスカバリー号」が到着し、山崎直子宇宙飛行士らSTS-131(19A)ミッションのクルーとの共同作業を開始した。
4月には、「蛋白質ユビキチンリガーゼCblを介した筋萎縮の新規メカニズム(Myo Lab)」実験と、「宇宙放射線と微小重力の哺乳類細胞への影響(Neuro Rad)」実験を実施。
前者は、筋肉の中のひとつのタンパク質(Cbl-b)に注目して新規筋萎縮メカニズムを明らかにするのが目的で、後者は、神経細胞への宇宙放射線の影響を遺伝子レベルで網羅的に調べるとともに、ミトコンドリアを介した細胞死(アポトーシス)に関わっている遺伝子を詳細に調べるのが目的。
4月30日から5月5日にかけては、ソユーズ宇宙船(21S)の移動飛行やSTS-132ミッションに向けた準備などを行った。
6月2日午前9時04分、オレッグ・コトフ、野口聡一、ティモシー・クリーマー宇宙飛行士が搭乗したソユーズ宇宙船(21S)が、ISSから分離。
6月2日午後0時25分、ソユーズ宇宙船(21S)はカザフスタン共和国に着陸。野口宇宙飛行士らの宇宙滞在期間は163日となった。
ビデオライブラリ「SPACE@NAVI-Kibo WEEKLY NEWS 第105号」